2025.07.21
学びの設計は言葉から始まる──3つの学習モデルの違いと戦略的使い分け
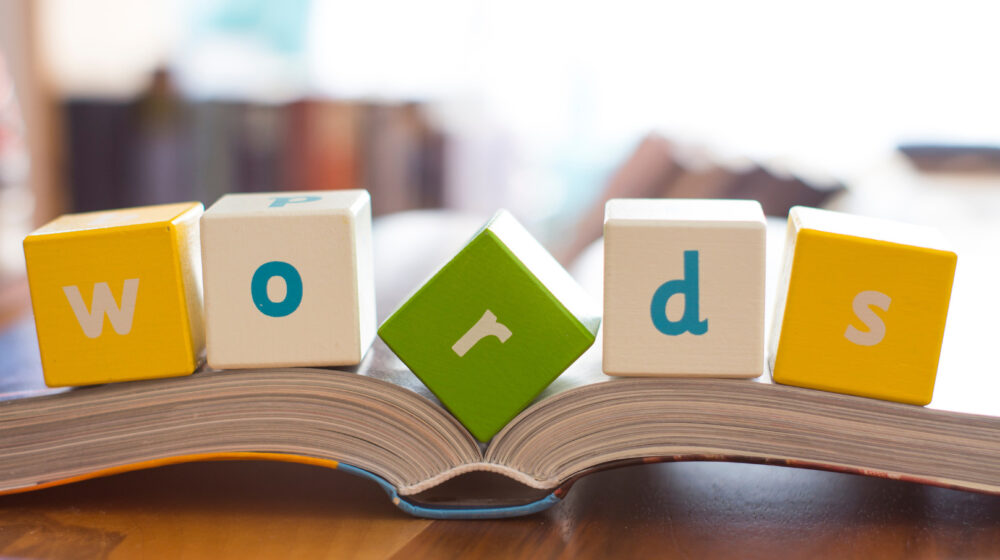
オンラインと対面の両立が当たり前となったいま、「ハイブリッド学習」や「ブレンディッド学習」、そして「ハイフレックス学習」という言葉が、企業研修や教育現場で頻繁に使われています。しかし──その言葉、本当に正しく使えていますか?
一見似ているこれらの言葉。ですが、その背後には、まったく異なる“設計思想”があります。もし違いを理解せずに使っているとしたら、それは学習効果のブレーキになるかもしれません。
大切なのは、「どんな技術を使うか」ではなく、「なぜそれを選ぶのか」。本記事では、3つの用語の歴史的背景と設計思想の違いを読み解きながら、教育設計者・人材開発担当者がいま立ち戻るべき視点を整理していきます。
1.歴史に学ぶ:テクノロジーと危機が形成した用語の背景
第1フェーズ(2000年代):ブレンディッド学習の黎明期
インターネットの普及に伴い、対面授業とオンライン技術を組み合わせる「ブレンディッド学習」が登場しました。この時期の中心的課題は、非同期・非対面環境でいかにして「社会的実在感(Social Presence)」を醸成するかという点でした。
第2フェーズ(2010年代):反転学習の台頭
スマートフォンとブロードバンドの普及により、「事前に動画で知識を学び、教室ではアウトプット中心の活動を行う」反転学習が広がりました。これはブレンディッド学習の実践的かつ人気の高い一形態として定着します。
第3フェーズ(2020年代):パンデミックとハイブリッド学習の急増
COVID-19パンデミックにより、学習者が一堂に会することができなくなり、「いかに同時に指導するか」という物理的・ロジスティクス的課題が表面化。Zoomなどのビデオ会議ツールを活用した同時参加型の授業形式が急速に導入され、「ハイブリッド学習」という言葉が一般化しました。特に日本ではこの初体験が強く印象づけられ、「ハイブリッド」が包括的な意味で使われるようになったのです。
第4フェーズ(現在):ハイフレックス学習の登場
「ハイフレックス学習」は、学習者が自身の状況に応じて参加形態(対面/リアルタイムオンライン/オンデマンド)を自由に選択できるモデルとして登場しました。学習者主体の柔軟性を最大限に重視するアプローチです。
2.設計思想の違いを読み解く:届け方と構造と自由度

ブレンディッド学習: ペダゴジー(学習設計)を起点とした教育モデル。目的に応じて、対面・非対面、同期・非同期、AIやメタバースなど、あらゆる手段を戦略的に組み合わせて設計されます。学習者の行動変容や成果を念頭に、どの活動をどの順番で、どの方法で行うかを精緻に設計する包括的アプローチです。
ハイブリッド学習: モダリティ(参加形態)を起点とした教育モデル。対面とオンラインの同時提供など、届け方の多様化に対応するために発展してきました。特に大学などの高等教育で、物理的制約を乗り越えるための実装として用いられました。
ハイフレックス学習: 学習者の自由選択を前提としたモデル。同一の学習機会に対して、学習者が「どこで」「いつ」「どのように」参加するかを柔軟に選べるよう設計されます。設計者側には複数モダリティで同一の学習効果を担保するという高度な設計が求められます。
3.言葉の使い分けが設計の質を左右する
これら3つの言葉は、単なる言い換えではありません。それぞれが異なる課題意識から生まれ、異なる設計アプローチを前提とした概念です。
- 「ブレンディッド」は設計視点の言葉:どのように学びを構造化するかに焦点
- 「ハイブリッド」は実装視点の言葉:どのように届けるかという現実的対応
- 「ハイフレックス」は選択権の拡張:学習者にどこまで委ねるかという哲学
これらを混同してしまうと、設計の目的や評価の基準が曖昧になり、結果として効果的な学習体験を生み出しにくくなってしまいます。
まとめ:言葉を整えることが、学びを整える第一歩
教育も研修も「言葉」から設計が始まります。定義があいまいなままでは、学習体験もまた曖昧になります。似て非なる「ブレンディッド」「ハイブリッド」「ハイフレックス」という用語を、思想レベルで正確に使い分けられるかどうかが、学びの質を大きく左右するのです。
これからの教育設計では、「どんな手段を使うか」だけでなく、「なぜそれを行うのか」という目的から思考を始める姿勢が求められます。曖昧な言葉に頼るのではなく、学習者にとって意味のある設計を選び取っていく──その判断力こそが、教育実践者の専門性を支えていくのです。
あなたの現場で検討している学習は、どの考え方に基づいて設計するとよさそうですか?